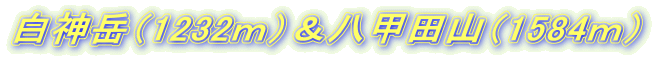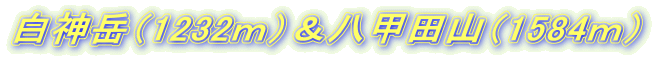10月15日(土)
日立中央IC(8:50)= 常磐道・東北道・秋田道 = 能代IC(14:35) 十二湖入口(15:35)→十二湖散策
= 深浦町 松神 「森山荘」(16:15着) |
白神岳 10月16日(日)

駐車場位置
宿(6:40発)= 白神岳登山口P(6:55発)→ 二俣分岐点(7:30) →
最後の水場(8:05) → 蟶山分岐(8:40) → 白神岳(10:20−11:20) →
蟶山分岐(12:40) → 白神岳登山口P(14:00着)
|

登山口駐車場 |
小屋の背後から舗装された林道を10分ほど進むと、標柱と案内板の立つ小広い広場に出る。
林道はここで終点となり、本当の登山口に着く。 途中の二俣分岐点までは、白神川の谷に面する蟶山南東斜面の中段を進んで行く。 |
二俣分岐点で右方に谷沿いの道を分けた後、やや急な坂道となる。しばらく南向きの斜面を登って行くと、沢水が多く流れる最後の水場に到着する。
樹林の中をジグザグに近い形で登り、蟶山分岐に出る。蟶山から続く尾根の上を東へ進む。時々下り坂を挟みながら、着実に高度を稼いで行く。途中の樹間から、昨夜の宿・森山荘の海岸線が覗く。
|

避難小屋とトイレ

岩木山 |

森山荘がある岬

「ガンガラ穴」駐車場から稜線上の白い点が山頂のトイレです
|
足下の海岸線の方はたいへん良い天気だが、白神岳の山頂方向はガスの中である。やがて木々の高さが急に低くなり、霧立つ笹原に出て森林限界に達する。
少し晴れ間が覗くようになる。森林限界から一登りで、不意に白神岳稜線に出る。
白神岳の主稜線に出て、十二湖・大峰岳方面からの登山道が左から合流する。やがて笹原に小屋が2棟立つ山頂の一角に到着する。
最初の小屋はトイレ、続いて堅牢な避難小屋が立つ。15〜20人ぐらいは収容可能である。
山頂に着くと東側の視界が一気に開ける。すぐ東に奥白神岳、その右肩に岩木山が雄姿を見せる。やがて全方向の雲が霧散して絶好の好天となる。感動的な眺望が広がる。
西に日本海の大海原が広がり、南には能代港、南東には白神山地の核心部の山並み、そしてすぐ北東に白神山地の最高峰である奥白神岳、さらにその奥の岩木山と、最高のパノラマである。
昨夜の宿・森山荘や登って来た尾根などもはっきりと確認できる。 |
白神岳登山口P(14:10発) = 鯵ヶ沢町(15:35) = 岩木山八合目(16:30-16:40)
岩木山神社(17:00) = 黒石市板留温泉(18:00着)
|
八甲田 10月17日(月)

駐車場位置
宿(6:40発)=酸ヶ湯P(7:15発)→ 地獄湯沢(8:05) → 仙人岱(8:35) →
八甲田大岳(9:25-9:40)→大岳避難小屋(9:55)→ 上毛無岱(10:45−11:25)
→ 酸ヶ湯P(12:20着)
|

酸ヶ湯への下り斜面 |
酸ヶ湯を出発し仙人岱への登山道に入る。
初めは笹藪の中の緩い階段だが、途中からぬかるみの多い樋状の道となる。歩きにくい。
やがて、火山噴気により植生のない地獄湯沢に出る。木道橋で対岸に渡り、急坂を登り詰めて行くと、広く平坦な仙人岱の一角に出る。
|
笹藪の中の木道を進むと、南方の立派な避難小屋への道を分けて、仙人岱・八甲田清水のほとりに出る。
ここで休憩する。そのすぐ先から東へ向けて、小岳を経て高田大岳へ到る道が分かれて行く。 仙人岱をあとに南側から大岳の急斜面に取り付く。
風雪等で矮小化した青森椴松の樹林帯を登って行くと森林限界となる。
|

仙人岱
|

大岳避難小屋 |
山頂が近くなり、崩落防止の蛇籠が連なる斜面をジグザグに登り行く。鏡沼の水は登山道まで溢れている。
やがて左側に小祠が現れ、間もなく山頂に到着する 人気のない山頂で薄ら寒いので、早々に下山する。 |
湿原の木道をもう暫く進み、板敷きの立派な展望所で昼食にする。宿で作ってもらった弁当を広げる。
青空の下、広い湿原の中での昼食は気持ちが良い。休憩後、下毛無岱の大階段へ向けて出発する。
|

毛上無岱 |

睡蓮沼 |
広い湿原が続く毛無岱は、高低差およそ50mの崖で上毛無岱(東側)・下毛無岱(西側)の2段に分かれる。
境目に木造の長い階段が掛かる。階段を慎重に下り、木道に出る。階段下の右手林中には、冬季用の毛無岱避難小屋が建つが、現在は使用不可である。
下毛無岱を一気に踏破して落葉高木の樹林帯に入り、酸ヶ湯へ向かう。 |
酸ヶ湯P(13:20発) = 睡蓮沼 = 酸ヶ湯 = 黒石IC(14:30) = 国見SA(夕食)
= 日立中央IC(20:55)
|

白神山地

海岸からの白神山

上毛無岱

田茂萢岳と井戸岳

睡蓮沼 |