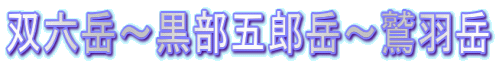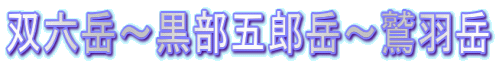7月31日(木)
日立中央IC(18:10) = 常磐道・中央道 = 談合坂SA(20:55−21:30)=松本IC(23:05) =
新穂高・無料駐車場(0:55着)

駐車場位置
|
|
8月1日(金)
新穂高温泉P (5:50発)
↓
ターミナル広場(6:00−6:15)
↓
笠新道入口(7:10)
↓
ワサビ平(7:30)
↓
小池新道入口 (7:50)
↓
秩父沢(11:20−11:40)
↓
シシウドヶ原(0:30−11:00)
↓
→鏡平山荘(11:45-12:55)
↓
弓折乗越(14:05−14:15)
↓
双六小屋(15:15着) |

槍ヶ岳 |

鏡平山荘 |
5時過ぎに起床して朝食を取り、食糧分配などの準備をして出発する。広い有料駐車場を過ぎて、バス停や登山指導センター、アルペン浴場などが並ぶ新穂高温泉ターミナルの広場でトイレ休憩する。
駐車場から左折して蒲田川(がまたがわ)に架かる橋を渡り発電所の前から北進して蒲田川左俣へ進んで行く。
笠ヶ岳・抜戸岳に発する穴毛谷の荒れた沢を対岸に眺めながら左俣谷左岸を進む。中崎橋で右岸に渡り、旧笠新道入口を過ぎて笠新道入口に到着する。
ここにはワサビ平小屋から引かれた美味い水が流れており、休憩して喉を潤す。森の中にビールをデポする。
|
ワサビ平小屋を通過した後、約20分で「小池新道」登山口に到着する。登山道は石畳や階段に近く良く整備されているが、左の中抜戸沢・上抜戸沢が押し出した大量の岩塊中をうねるように登って行く。所々で近くに雪渓が残る。
沢の水音が近くなり、秩父沢に飛び出して木橋で渡る。ここで暫時休憩する。すぐ上に雪渓が迫っており、手が痛くなるほどの非常に冷たい沢水が流れる。水筒を冷水で満たして出発する。 |

槍ヶ岳(弓折乗越より) |

鷲羽岳と双六小屋 |
イタドリヶ原、シシウドヶ原を経て小広い平地に小さな池や湿地が散らばる鏡平に到着する。ここで昼食を取る。
山荘の前から主稜線までの登山道が見渡せる。あと1時間の登りで主稜線である。
稜線に出ると南の笠ヶ岳から今から向かう双六岳までの主稜線が初めて見渡せる。また、東の雲の中に槍・穂高連峰全体の基部を見渡すようになる。更に北方に樅沢岳から槍ヶ岳に連なる西鎌尾根もその全容を見渡すことができた。
雪渓が残る花見平を過ぎ、しばらく標高2600m前後のアップダウンを繰り返して進めば双六小屋が見えてくる。
小屋は混雑により2人で布団1枚の割当てであった。 |
|
8月2日(土)
双六小屋(5:35発)
↓
双六岳(6:50−7:10)
↓
三俣蓮華岳(8:10−8:45)
↓
黒部五郎小舎(10:05−11:05)
↓
黒部五郎岳カール雷岩上(12:00−12:20)
↓
黒部五郎岳肩(12:50)
↓
黒部五郎岳(13:00−13:30)
↓
黒部五郎岳南カール壁末端(14:25−14:45)
↓
黒部五郎岳小舎(15:20着)
|
 朝の双六池と笠ヶ岳 朝の双六池と笠ヶ岳 |

双六岳への登りより |
朝食は先着順ということで、行列に並び4:30から朝食を取る。
小屋を出発し、西方にハイマツの中を約100m直登すると中の台地に出て、間もなく三俣山荘への巻道を右に分ける。更に雪渓が残る急斜面を一登りすると、双六岳南東面の広い頂稜に出る。
双六岳の頂稜は、槍ヶ岳を南東に望む著名な撮影地点であり、雑誌などに良く掲載される場所である。 双六岳山頂へ向かう道の背後に、朝日を受けた槍ヶ岳の穂先がシルエットのように浮かぶ。なかなかの上天気である。
それぞれに思い思いの写真を撮る。
|
双六山頂からは360度の大展望が開ける。すぐ北に丸山と三俣蓮華岳、その左奥に薬師岳、右に剣・立山、水晶岳(黒岳)、鷲羽岳・野口五郎岳、東には燕岳・大天井岳、南東に北鎌尾根と槍・穂高連峰、焼岳、乗鞍岳・御岳、南に抜戸岳・笠ヶ岳、西に遠く白山と近く黒部五郎岳と、好天に恵まれて北アルプス周辺の名峰をほとんど全部眺めることができる。
双六岳山頂を後に三俣蓮華岳へ向かう。急斜面を下って先ほどの中道に合流し、南北に長い丸山の頂稜部を通過する。 |

定番写真 |

水晶岳と鷲羽岳 |
もう1度鞍部まで約70m下って登り返すと三俣蓮華岳山頂へ到着する。
三俣蓮華岳は主稜線から北東に突き出した南北2つの小ピークを持つ山頂である。その間100mも離れていない。
北峰には三角点や標柱が立っており、その南東・北東・北西の3面は切れ落ちている。また北峰の南東側に三俣山荘から急登してくる登山道がある。
一方、南峰には「長野・富山・岐阜三県の境」標柱が立ち、ここから西方に黒部五郎岳方面への道が分岐する。
好天のもと登山者が多く集う山頂で北アルプス最深部の雄大な眺望を楽しみながら、しばし休憩する。 |
三俣蓮華岳の南峰を後に西へ進みハイマツが茂る稜線を下り始める。さほど急な下りではないが短時間で高度を下げて行く。やがて三俣山荘からの巻道に合流する。
見晴らしの利く地点(標高約2620m)から南西へ向きを変えると小さな雪渓が続く。その先の森林限界の手前で黒部五郎岳を間近に望みながら小休止する。
灌木帯に入ると石のゴロゴロした急な下りが続くがやがて黒部五郎小舎が立つ黒部乗越に下り立つ。
今夜の宿泊予約を済ませて、小屋の前で昼食を済ませ、黒部五郎岳に向かう。 |

黒部五郎岳 と黒部五郎小舎 |

黒部五郎小舎 |
最初はダケカンバやナナカマドの灌木帯を進む。途中で雪解けの小さな沢を何度か渡る。更に進み高度を上げて行くと灌木も無くなり、大岩が散乱する広いカール底を登るようになる。
大雪渓から流れ出る豊富な冷水で喉の渇きを潤す。
カールの壁を登りきると、北ノ俣岳・太郎平小屋への分岐点となる黒部五郎岳の肩に着く。山頂へは岩塊の斜面をジグザグに登って行く。
小舎への下りは「二度とこれないかもしれない」ので稜線コースを下ることにした。
大岩の割れ目を飛び越えたり岩稜を急に下降したりと、割合に変化のある稜線で面白い。 |
 双六岳からの展望 双六岳からの展望 |
8月3日(日)
黒部五郎岳小舎(5:20発)
↓
三俣蓮華巻道分岐(6:25)
↓
三俣山荘(7:10−7:20)
↓
鷲羽岳(8:30−9:00)
↓
三俣山荘(9:40−9:50)
↓
三俣蓮華岳巻道分岐(10:50)
↓
双六小屋(12:35−13:30)
↓
弓折岳分岐(15:00)
↓
鏡平山荘(15:35着)
|

朝焼けの黒部五郎岳 |

薬師岳 |
三俣蓮華岳へは向かわず、稜線北側の巻道に入る。
三俣蓮華岳北稜を成す小さな尾根を乗り越えると三俣山荘が見えてくる。ここで一息入れる。
三俣山荘は周囲をハイマツで囲まれた谷間に立つ。南東方向に槍ヶ岳と北鎌尾根が望める。
目前に大きく迫る鷲羽岳に取り付く。登山道は最初少し緩やかだが、間もなく急登となる。砂礫が重なる稜線をジグザグに進む。なかなかきつい登りである。やがて、右下方に火口湖の鷲羽池を望むようになると、間もなく山頂である。 |
三俣山荘の前で一息入れて、双六小屋を目指す。
小屋からは三俣蓮華岳山頂へ向けて緩やかに約200m登る。山頂の直下までハイマツを縫うようにだらだら登りが続く。やがて三俣蓮華岳山頂南東直下の巻道分岐点に着く。分岐点から巻道に入る。稜線通しの道に比べるとアップダウンは少ないが、登下降が続く道である。
双六小屋の前のテラスでゆっくりと昼食を取る。双六池付近には、クロユリの花が咲いていた。
鏡平山荘では、南側の別館(新築されたばかりの様子)の個室1部屋に7名分を割り当てされた。一息ついて鏡平名物のかき氷を味わう。 |

黒部五郎岳 |

穂高(鏡池より) |
16時30分過ぎぐらいから、雲の中で見えなかった槍・穂高連峰がその勇姿を見せ始める。
テラスにいた登山者から大きな歓声が上がる。山荘から南方へ木道を進んだ池のテラスで、雲が流れる中に夕日を浴びて光輝く槍・穂高連峰の写真を撮る。
 鏡池 鏡池
|
  
|
  
|
|
8月4日(月)
鏡平山荘(7:10発)→ 秩父沢(8:30−8:40)→ 小池新道入口 (9:20)→
ワサビ平小屋(9:40−9:55)
→ 穂高温泉 左俣林道ゲートニューホタカ(10:45−入浴 −12:15)
|
今日はあいにくと明け方から雨模様である。遅い朝食を取り、雨具を着て雨の戸外に出る。今日は木道も石畳も滑りやすいので、要注意である。
林道ゲート(車止め)のそのすぐ下手の右にあるロッジ「ニューホタカ」の日帰り温泉で汗を流すことにする。その間車の所有者がかなり下手の無料駐車場から回送し、着替えを出して温泉に浸かる。この温泉は内湯のほか、左俣沢の岸にも露天風呂があり、料金はいずれも1人500円である。4日間の汗とホコリをサッパリと流して、帰途に着く。
ニューホタカ(以前はホテルであった。現在は登山者向け宿泊のみのロッジ、食事なし。)の管理人に昼食のお薦め場所を聞き、道の駅「奥飛騨温泉郷上宝」に立ち寄る。道の駅の食堂「たぬき」で飛騨牛串焼き定食を食する。値段の割には少々期待はずれの内容であった。 |
ニューホタカ(12:15発) = 新道の駅・ 奥飛騨温泉上宝(12:30-13:15)昼食 =
松本IC(14:50 )= 諏訪湖SA(15:10-15:35) = 談合坂SA(16:45-17:05)=
八王子TB(17:40)=守谷SA(20:45−21:20)=日立中央IC(22:30着)
|