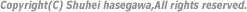| ■ 2003年12月 主な活動 | |
| 1日 | 第4回定例県議会(本会議・一般質問) |
| 2日 | 第4回定例県議会(保健福祉委員会) |
| 3日 | 東海村議会議員 馬目暢之後援会臨時総会 参院選 加藤としゆき激励集会 |
| 4日 | 民主党県連 総支部幹事長連絡会議 民主党県連事務局 国会議員秘書団連絡会議 |
| 5日 | 日立グループ議員団 幹事会 |
| 6日 | 原子力ファミリー世話人会 |
| 7日 | 地元行事 |
| 8日 | 議事整理 |
| 9日 | 第4回定例県議会閉会(本会議) 【詳細記事へ】 十王町議会議員 渡辺正幸後援会臨時総会 |
| 10日 | 日立労組日立支部 地域対策局会議 |
| 11日 | 民主党県連 第5総支部幹事会 |
| 12日 | 細田武司県議会議員 藍綬褒章受賞祝賀会 |
| 13日 | イラクへの自衛隊派遣反対街頭宣伝 |
| 14日 | 知人告別式 |
| 15日 | 連合茨城・民主党県連 三役懇談会 日立市秋の叙勲 国家褒章受賞祝賀会 日立市議会議員 西川光世後援会総会 |
| 16日 | 平成16年度県政要望 知事に提出 【詳細記事へ】 |
| 17日 | 地元後援会「修峰会」幹事会 |
| 18日 | 日立労組日立支部 地域対策局会議 |
| 19日 | 保健福祉委員会 県内調査 【詳細記事へ】 |
| 20日 | 民主党県連 三役会議 常任幹事会 |
| 22日 | 連合茨城 総合研究所会議 |
| 23日 | 知人告別式 |
| 24日 | 年末挨拶廻り |
| 25日 | 都市計画審議会 |
| 26日 | 日立労組日立支部 地域対策局会議 年末挨拶廻り |

 第4回定例県議会 第4回定例県議会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年最後となる第4回定例県議会が例年より一週間程早い12月9日閉会となった。 早期開催の原因となった、県職員の給与引下げに関する条例改正案、核燃料取扱税に関する条例改正案等が原案通り賛成多数で可決された。 また、最終日には共産党から「イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書」が提出された。我々は共産党とは議会活動において常に一線を画してきたが、民主党本部からの「地方議会における自衛隊派遣反対決議採択の取り組み」の要請に基づき共産党と同調するのは不本意であるが、意見書提出に賛成をした。 さらに保健福祉委員会では付託された案件はなかったものの山本保健福祉部長より報告があった「放射線利用高度医療施設整備基本構想策定委員会」の検討状況について「PET検査体制整備」、「粒子線治療体制整備」、「ホウ素中性子捕捉療法関係」の3つの専門部会を設置し、来年3月の基本構想の決定までいよいよ佳境にはいることから各々の整備費について保健予防課長に質すとともに費用対効果つまりコストパフォーマンスを十分考えて対応するよう意見をのべた。 次に福田企業局長より報告があった八ッ場ダム、湯西川ダムの基本計画変更について大幅な建設費アップになるため水需要の見直しや建設費の削減のための努力が十分反映されているか次の定例県議会まで十分な議論を行なっていきたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 平成16年度県政要望 知事提出 平成16年度県政要望 知事提出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来年度の県の施策に反映させるべく県政要望書を橋本知事に提出した。 今回は新規45項目を含む合計376項目を要望したが、ひとつでも多く具現化するよう引続き努力していきたい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 保健福祉委員会 県内調査 保健福祉委員会 県内調査 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月19日保健福祉委員会の年内最後の調査として「筑波大学陽子線医学利用研究所センター」を調査した。 第4回定例県議会中の保健福祉委員会で山本保健福祉部長より報告のあった「放射線利用高度医療施設整備基本構想策定委員会」の検討状況について、陽子線治療等の調査を所管の委員として充分に行なう必要があるため実施されたものである。 秋根康之センター長より陽子線治療装置の説明、実際治療をしている患者さんからの聴取等行なったが、私がかねてから主張している県民にあまねく波及効果が高く、コストパフォーマンスが高いのは陽子線治療であるとあらためて確信をした。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||