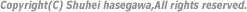| ���^�ɂ����锭���� |
| ������ |
�����v�| |
���َ� |
�����v�| |
| ���J��ψ� |
���N�x�̍��̐Ŏ��͓����\�Z�Ŗ�46���~�ł��邪�A�����_�ł̌��ʂ���37���~���x�Ƃ���Ă���B�{���̍��N�x�̐Ŏ����ʂ��́B |
�Ŗ��ے� |
��R�����̑�\����ɂ����āA�W�������_�̎��т͑O�N������Ł�13���A�����\�Z����129���~�̌��������Ɠ��ق����B
�����_�ł̍ŐV�f�[�^�ł���10�������т́A�O�N�����䂪��12.7���łR��̓��َ��Ɠ����Ő��ڂ��Ă��邱�Ƃ���A130���~���x�̌����ɂȂ�̂ł͂Ƃ݂Ă���B
���݁A��Ƃ���̃A���P�[�g�����Ȃǂ̌�����Ƃ��s���Ă��邪�A�ŋ߂̉~����f�t���̉e�����l�����邽�߁A�������������茩�ɂ߁A���m�Ȍ����݂��o���Ă��������B |
| ���J��ψ� |
�{�N�x�̐Ŏ������ݓ������炩�ɂȂ��Ă��Ȃ���A���N�x�\�Z�Ґ��ɂ��i�߂Ȃ��͂��ł���B
�W�����v�v�����ɒ�߂�{�N�x�̌��œ�4,086���~�͊m�ۂł���̂��B |
�����ے� |
�n������œ����܂߂������z�͖�162���~�ƂȂ錩���݂����A�Ŏ��̈�芄������t����s������t�������z�ƂȂ邽�߁A�S�̂Ƃ��Ă̌����z�͖�130���~�ƌ�����ł���B
�܂��A�����\�Z�Ґ����_��190���~�̌��Ǘ��������̌J�։^�p���v�サ�Ă���̂ŁA�����ւ̑Ή��ɉ����āA���̉��������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
������Ă��ސE�蓖�̊��p�ɉ����A���s�i�K�ł̂���Ȃ�\�Z�̐ߖɎ��g��ł��邪�A�����_�ł́A�����̋��z��S�ĉ����ł��錩���݂ɂ͎����Ă��Ȃ����߁A ����܂őΏۂƂ���Ȃ������Ŗڂւ̌�����Ă�̓K�p�g��⍑�̌o�ϑ�ɂ�����n���������������������Ă���Ƃ���ł���B
���������̉��A���㌈�肳��鍑�̒n���������������܂��āA���N�x�̗\�Z�Ґ��ɂ������Ă��������B |
| ���J��ψ� |
���ɂ�����Ŏ����ʂ��͌��������A�܂�����ŁA�����K������������K�v������̂ŁA�����ے��A�Ŗ��ے��ɂ͂���w�w�͂��Ă��炢�����B
���̗��N�x�̗\�Z�Ґ��́A���̐����������܂��āA�ǂ��ɗ͓_��u���l�����B |
�����ے� |
�m���̌f���������匧�Â���̂��߂̎{��A���̒��Ƃ��Č�����������d�_�ɕҐ����Ă����l���ł���B
�����������̒��ŁA�����������͂ł��Ȃ��̂ŁA�I���ƏW���A���ʁE���ʂ��݂Ȃ���[���x�[�X�ł̌�������O�ꂵ�Ă����B |
| ���J��ψ� |
�u�Y�Ƒ匧���琶���匧�ցv��u�[���x�[�X�Łv�͍��߂Ă̂��̂ł͂Ȃ��B
���́u���Ǝd�����v�́A�N���[�Y�ł������\�Z�Ґ��ߒ����I�[�v���ɂ������ƁA�����J�̊ϓ_�ő傫�����ڂ��ꂽ�B�����ے��̓[���x�[�X�ł���Ă���ƌ������A�����ɂ͂� ���킩��Ȃ��̂ŁA���J�Łu���Ǝd�����v�̂悤�Ȃ��̂����{���Ă͂ǂ����B |
�����ے� |
�u���Ǝd�����v�ɂ��Ă͗l�X�ȕ]�������邪�A��O�҂ɂ�蒼�ڋc�_���s�����ƁA���J�ōs�����Ƃ͈Ӌ`������ƍl����B
���ɂ����ẮA�����\�Z�̎d�オ��̍ۂɔp�~���Ɠ��������Đ������Ă��邪�A����ɍH�v���Ē��J�Ȍ��\�ɓw�߂����B
�u���Ǝd�����v�I�ɂ́A���N�x�t�悩��S�����ǂƂ̊ԂŎ������Ƃ̌����������{���Ă��Ă���B |
| ���J��ψ� |
��̓I�ɂǂ̂悤�ɗ\�Z�Ґ����s���Ă���̂��������Ȃ��B
�u���Ǝd�����v�́A�v���Z�X���I�[�v���ɂ��邱�Ƃɂ��A�^�ۗ��_�������N���邪�A���̗\�Z�͑S�Ăɂ��ċc�_�������グ��킯�ł͂Ȃ��B
�傫�ȉۑ�ɂ��Ă͎��O�ɐ������邪�A��\���̒��Łu���Ǝd�����v�̂悤�ɋc�_���I�[�v���ɂ��Ă����H�v�͂��Ă��炦�Ȃ����̂��B |
���������� |
�u���Ǝd�����v�����{������������́A�@�Z���ԂŌ��_���o���̂ŋc�_���[�܂�Ȃ��A�A���o�I�Ȉӌ����o�����A�B�����ʂ̕K�v�����l�����ꂸ�������D��̕]���ɂȂ肪 ���A�Ȃǂ̈ӌ����Ă��邽�߁A������O���ɉۑ��ʂ������Ă����K�v������B
�Ȃ��A���݂ł���O���č���o���c�̓��o�c���P���ψ���ɂ����āA�O���̖ڂɂ�錵�������ƃ`�F�b�N���Ă���A�������ƍč\�z�ƕ����ĐϋɓI�Ȏ��ƌ������ɓw�� �����B |
| ���J��ψ� |
�����łǂ������ł͂Ȃ��A��錧�Ƃ��Ăǂ����Ƃ������Ƃł���B
���������������ŁA�Z������Ђ�J�����Б�����{���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�m�����T���ڂƂȂ����̂�����A�����̊F�l�ɗ������Ă��炦���@�A����܂łƂ͈Ⴄ��@��������āA�I�[�v���ɂ��ׂ����̂̓I�[�v���ɂ���A���̂悤�ȃ`�������W �����Ăق����B |
|
|
| ���J��ψ� |
��R�����ɕ��ꂽ�S���������ʂ̕s�K���o���̋��z�ƍ�����ꂽ�w�E���z�Ƃ��قȂ闝�R�́B |
�w���� |
����͉̕�v�����@���w�E�����_�ѐ��Y�ȋy�э��y��ʏȂ̍��ɕ⏕���̎w�E�z�ł���A���̑S���������ʂ̑��z�Ɋ܂܂����̂ł���B |
| ���J��ψ� |
�s�K���o���ɂ��āA�{���ɖ�肪������̂Ɛ��x�I�Ȗ��ƍl������̂Ƃ͉����B |
�w���� |
��a���ࣁA��ꊇ����A����ւ���͎��I���p�ɂȂ���\���������Ă���A�܂����������������Ă��Ȃ��Ȃǂ̖�肪����ƍl���Ă���B
�u���N�x�[���v�⢑O�N�x�[����́A�葱���������K���ɔ����Ă���ʂ����邽�߁A�傢�ɔ��Ȃ��ׂ��ł͂��邪�A�s���Ɍq����\���͏��Ȃ����̂ƍl���Ă���B |
| ���J��ψ� |
��v�����@�Ƃ̉��߂̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂��B�܂��A�S���ł��R�Ԗڂɑ傫���w�E�z�ɋ����Ă���A������Ƃ������������ė��������߂邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B |
�w���� |
���߂̈Ⴂ�Ƃ��ẮA�����◷��ɂ��ẮA�����̕K�v����o��������͐����Ȏx�o�ł��邪�A�⏕���Ƃ̏[���Ƃ��ēK���ǂ����Ƃ����_����������B
11��11���ɉ�v�����@������\���ꂽ���A26�����A���z�łR�Ԗڂł��邱�Ƃ͏d��Ȃ��ƂƏd���~�߂Ă���B�����ɂ��l�ѐ\���グ��B
�w�E�z���������R�Ƃ��ẮA�����ӎ��̊���`�F�b�N�̐��̊Â��Ƃ��������ƈȊO�ɁA�s�w�����J����S����Q�ʂ̓��H�����ȂǁA�������Ƃ������A�N�x���̖����ȗ\�Z�� �s�����������߂ƍl���Ă���B
�w�E�z�̑傫�����Ƃ͑傢�ɔ��Ȃ��ׂ��ł���A������Ƃ������������s���ƂƂ��ɁA���ɑ��A�s�K���o���̍Ĕ��h�~�ɕK�v�Ȃ��Ƃ͌����Ă��������B |
| ���J��ψ� |
�����s�c��ŁA���^���Ă��ی����ꂽ���A���̂��Ƃɂ��āA���͂ǂ̂悤�ɔc�����A�܂��A�l���Ă���̂��B |
�s�����ے� |
11��24���̍����s�̗Վ��c��Ŕی����ꂽ���ẮA���̐l���@�����܂��A�E���g���̍��ӂĒ�o���ꂽ���̂ƕ����Ă���B
���Ƃ��ẮA���������������ƂȂǂ𗝗R�ɋ��^�팸�����{���Ă���s�����ɑ��Ă��A�܂��́A�l�����ւ̑Ή���������ŁA�X�̎s�����̍����ɂ��A�Ǝ��̑[�u ���K�v���ǂ����f����悤���������Ă���B
�����s�ł́A12��4���ɒ���J���ƕ����Ă��邪�A���̐����Ɍ����A�c��ɑ��Ďs�̍��������\���������A��������悤�A�ő���̓w�͂����Ă��炢�� ���|���������B |
| ���J��ψ� |
���b��_���̂ł���͐삪���a����Ă��鎖����m���Ă������B |
���E�y�n�v��ے� |
�V���A���y��ʏȂ̏��Œm���Ă����B |
| ���J��ψ� |
���b��_���́A�{�̔�������Ă��Ȃ��B������_���́A�{�̔�������Ă���B
���b��_�������~�ɂȂ�����A������_���̐��b��_���̑���Ɏg���Ȃ��̂��B |
���E�y�n�v��ے� |
���b��_���̎b�萅�����́A���|�I�Ɍ���L�搅���������A�����L�搅���͏��Ȃ����A������_���̎b�萅�����́A�����L�搅���Ŏg���Ă���B
������_������������A���݂̋����ʂł���A���b��_�����̐����Ȃ��Ă��A�����L�搅���͘d����\���̓[���ł͂Ȃ����A����L�搅���̐����͓n�ǐ��V���Ɣ��b��_ ���������悻�Q���̂P���Ȃ̂ŁA���b��_�����Ȃ���Θd�����Ƃ͓���B |