| 平成21年11月04日 | ||
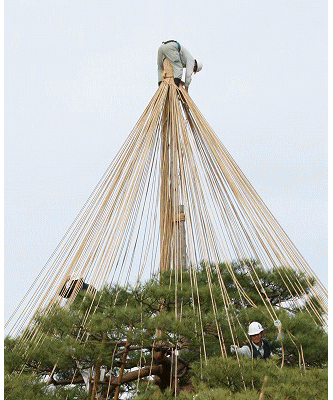 金沢 兼六公園の雪吊りは有名だ。11月4日、中学校のクラス会があるというので久々に金沢に行き、兼六園を訪ねたら、丁度、雪吊り作業の最中だったので、少しの間、足を止めて眺めた。私の頭では、「予め棒の先端に荒縄を必要本数縛り付けておき、それから棒を立ててやれば、何も高い所まで上がらなくて良いのではないか」などと勝手な妄想をしていた。ところが、写真のように、棒というより電信柱位いの太い柱であるがその天辺に登って、上から縄の方向を定めていた。やはりそうしないと、縄が一定の間隔で放射状にならないのだろうか。 これは、まさしく加賀鳶の仕事なのだ。そう、正月の出初式には「加賀鳶のはしご登り」が昔から有名で、今も伝統を受け継いで超人的な技を見せているが、同じだなぁと、見入ってしまった。 |
||
| 私の育った家(本多町)から公園までは歩いて15分しか離れていなかったので、子どもの頃はしょっちゅう遊びに行っていた。冬になると必ず雪吊りが張られるし、それは何も公園だけの特別なことでは無かったので、これが当たり前で、どこでも見られるもんだと思っていた。今しみじみ見ると、とんでもない価値のある造形美なんだなぁと改めて感じた次第。 ● 兼六園は、もともと金沢城の前庭として作られたもの。その“兼六”の由来・意味を知らなかったが、最近になって分かったのでメモしておきましょう。 1822年(文政5)加賀藩12代藩主前田斉広(なりなが)の時、中国の宋時代の詩人李格非の書いた洛陽名園記の文中から採って、宏大・幽邃(ゆうすい)*1・人力・蒼古(そうこ)*2・水泉・眺望の六勝を兼備するという意味で「兼六園」と命名したとのこと。 *1幽邃(ゆうすい)・・・奥深くて、もの静かな景色 *2蒼古(そうこ)・・・年代を経た草木が青々としているさま ● ついでにもう一つ、徽軫(ことじ)灯篭の名前の意味だが、次の通り。 この灯篭の足が琴の糸を支える琴柱(ことじ)の形をしていることから名づけられたものである。 |









