
 |
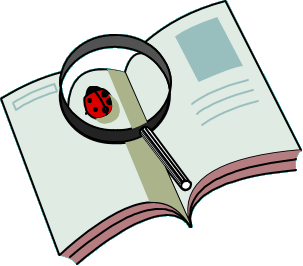
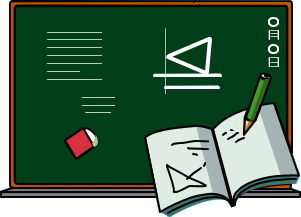

| 釉薬のいろいろ | 焼き物には、どうして釉薬を使うのでしょうか。はたして化粧をし、着飾って美しく見せたいだけの理由からでしょうか。 どうも、それだけではなさそうです。 主な原料を下に示す。(単位g) | 備前焼などは、釉薬を用いずに素地肌を見せて、その自然で素朴な味わいが、特色としています。焼成時に、炎の力で出来た灰釉の色や作意の無い模様は私達を魅了します。 何故でしょうか?それは備前土が特に焼き締まりの良い性質を持った土だから、釉薬を必要としないのです。 これが焼き物の理想と私は、考えています。 |
| 透明釉 塩釉 |
先ずは素地土(白系)を使った透明釉に挑戦します。実験方法はA=土+灰、B=土+長石、C=土+3号釉の2種混合をベースに、他の原料を少しずつ加えていく。納得のいくオリジナルの透明釉が出来るまで、さまざまな調合比を試してみました。 完成品=土(40)+灰(60)+長石(40) |
その他にも、そのような土はありますが、一般的には吸水性がたかく、水漏れがある陶土が多いので、それを防ぐために釉薬をほどこしているものと考えます。それでも、焼き締めの本来の味や陶土の色を残したいときには、透明釉や塩釉と言われるものを用いたら如何でしょうか? |
| 志野焼 | 濃い目の釉をワザとムラ掛けすることで、厚い部分は淡雪のような白色に、薄い部分にはほんのりと火色が現れます。また下絵を施し、釉の向こうに見え隠れさせる手法も、志野釉ならではの独特の味わいを醸し出します。 完成品=平津長石(83〜91)+蛙目粘土(9〜17) |
備前焼のように、窯地とその地で採れる土によって知られているものが一方であるとすると、他方に釉薬や絵付けや焼成温度によって特色を出しているものがあります。 一目瞭然、雪の掛かったような柔らかな白色の景色を見せる志野焼はその一つです。 志野の産地は瀬戸ですが、その地の陶土で作るのが常識です。そして、志野釉の主成分は長石です。「雪景色」を出してみるのに、素焼き後に赤茶色になる志野土と同じような栃木県茂木町産の「もてぎ土」で試してみてはどうでしょうか? 正道とは言えませんが、このようにそういをめぐらすことも一興かと思います。 |
| 飴釉 柿釉 |
光沢のある透明釉に、鉄分を少しずつ加えていくと、茶色、褐色、黒色と次第に色が濃くなっていきます。民芸品の瓶などでも良く見られるように、素朴な風あいが特徴です。 完成品=長石(74)+石灰(11.2)+珪石(7.4)+酸化鉄(7.4) |
益子焼きの水瓶を良く見かけることがありますよね、あれは飴釉。それに似た柿釉。鉄分の多い釉薬を使うと茶色や暗褐色の素朴な色を出せます。 |
| 天然栗皮灰 天然粉末ワラ灰 天然モミ灰 天然土灰 天然ワラ灰 合成土灰 合成ワラ灰 |
天然ワラ灰 ワラ灰とは、稲ワラを燃やして作る灰のこと。他の草木灰と異なり、珪酸分が非常に多いため、媒熔原料の土灰とは区別して使います。このワラ灰を加えることで、白く不透明な釉になるのが特徴です。 完成品=長石(40)+合成土灰(30)+ワラ灰(30) |
天然灰や合成灰を使用すると、釉薬の溶け具合、色あいなどを変化させる酸化金属類が複雑に含まれているので、自然の持つ力を利用して、より味わい深く心のなごむ釉薬を作り出すことが出来ます。 |
| 織部釉 白萩釉 信楽釉 黄瀬戸釉 黄伊羅保釉 白マット釉 |
独特の深い緑色は、酸化銅が透明釉に溶けて、一部は釉薬の成分と化合し、残りの銅分が細かい粒となって釉中に浮かんでいる状態で得られます。釉の中にアルカリ分多いと青みが強く、石灰や珪酸分が多いと緑味が強くなりますが、銅分を多くし過ぎると、緑を超えて黒味を帯びてしまうので注意。 まずは調合例を参考に挑戦されては 完成品=長石(56)+合成土灰(40)+酸化銅(4) |
私の好きな釉薬の1つに織部釉があります。古田織部の好みで作られた美濃産の陶器のうち、青織部に用いられる濃緑色の銅釉が織部釉。 |

素焼きの終わった器に釉薬を施すことを施釉と言いますが、その方法には、代表的なものとして下記のような物があります。
| 浸しがけ(ずぶがけ) | 流しがけ | 刷毛ぬり | 吹きつけ | 二重がけ |
| 器の一端を持ち、釉薬の中にとっぷりと浸す。 器を釉薬から引き上げたら、指などで浸らなかったところを筆などにて同じ釉薬を塗る。 平均的にかけるか、濃淡が出来るようにかけるかは、何回かの挑戦によって試されたい。 |
釉薬のバケツの上で柄杓に入れた釉薬を器に満遍なく流しながら掛けていく。 濃淡を付けるか、同じ厚みの釉薬にするかは、出来上がり状態を見て試されたい。 |
刷毛に釉薬をたっぷりと含ませ、出来るだけ迅速に縁から内側、そして縁へと刷いていく。 そしを平行均等に繰り返し、器の全てをおおいつくす。 この手法を用いた名品に、益子焼の人間国宝・浜田庄司の「絵刷毛目鉢」などがある。 |
器を手動ろくろの上に載せ、回転させながら霧吹器で満遍なく釉薬を吹き付けていく。 慣れると綺麗に施釉ができ、焼き上がり後も平均した釉薬のかかり具合となる。 |
言葉の通り浸しがけした後にもう一度同じ釉薬か、又は別の釉薬を二重にかける。 施釉の方法も流しがけと吹きつけの組み合わせ、刷毛ぬりと吹きつけ等いろいろの組み合わせで、味わいのある焼き上がりが出来ます。 |